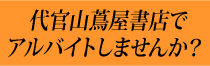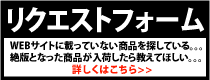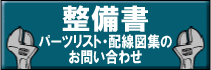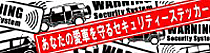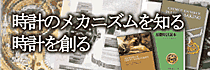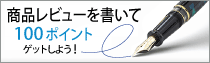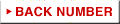操作感のないものが・・・失われつつある操作感
|
1980年代のジャガーのドアの閉まる音が好きだった。その音が聞きたくてジャガーに乗っていた。急いでいるときでもゆっくり締めて、カシャっと心地よいそしてしっかり閉まる音を楽しんでいた。 ライカのMP4にビゾフレックスを付けていたので、シャッターを落とすとミラーが閉まったままになってミラーアップしない。要するにシャッターを押すと真っ暗になる。今撮ったシーンは頭の中の残像のみだし、ましてその後もっとよいシーンがあったかもしれないのに、連写できないからそれまでになる。だからライカで撮るときは絶対これだという瞬間を真剣に追うことになる。何よりライカで撮ったときのモノを操作して残る残存感。これだと思ってシャッターボタンを押した時、音と感触は映像とともに残る。だから後日ライカで撮った、その瞬間を捕らえたその写真を見たら、その状況は鮮明に今も残る。 アナログ時計の秒針のかすかな音から歯車の動きは想像できるがメカニズムは複雑すぎて分らないし、ましてトゥールビヨンなどもっと分らない。メカニズムがすべて分らなくても操作感は分る。またデジタル化が進む世の中で、操作感自体が失われていくとは思わない。 iPhoneのタッチパネルのスクロールや拡大縮小などのスムースな操作感は、ほとんどの人に受け入れられているから世界中で売れている。iPhoneの欠点をあげれば文字化けからいろいろあってきりがないが、この操作感については最上級でこの操作感ゆえに手放せない。手に取るものの必須条件は、そのものの優秀性や機能性もさることながら操作感が絶対条件である。 よい操作感とは、第一に操作する上で不快を感じさせないと言うことがまずあるだろう。操作反応は早すぎても遅すぎても良くない。人の感性に適応する速度である。感触と操作ストロークがその操作をする上で感覚的に見合っていることだ。また何かをする上で無音ということに違和感がある。操作音は電気的に作られるべきではないし、メカニズム的にもあえて作られていたらなおさらだ。第二に操作することが楽しみにつながるものでなければならない。操作し心地といったらいいだろう。それがタッチ感であったり、気持ちよい重さ、反動、響きだったりする。  昔、横浜元町でハンドメイドのジッポーライターを買った。外見はどうと言うことはない。ジッポー本体を入れる外側の厚さが3mm以上あるのでポケットに入れると穴が開きそうなほど重い。この重さは明けたときの音に拘って作ったためこの厚さが必要だったと言われ納得した。開けたときの音はピーンと響き渡る。この音を聞いてタバコに火をつけるから、いつものタバコでも美味い。この操作音が命の道具。だから20年もデスクの上にある。第三に手に馴染むものでなければならない。手に馴染むとは、手が抵抗なく受け入れているということだろう。手が欲しがるような、手が勝手に判断して知らないうちに掴んでいるようなそんなものだろう。 昔、横浜元町でハンドメイドのジッポーライターを買った。外見はどうと言うことはない。ジッポー本体を入れる外側の厚さが3mm以上あるのでポケットに入れると穴が開きそうなほど重い。この重さは明けたときの音に拘って作ったためこの厚さが必要だったと言われ納得した。開けたときの音はピーンと響き渡る。この音を聞いてタバコに火をつけるから、いつものタバコでも美味い。この操作音が命の道具。だから20年もデスクの上にある。第三に手に馴染むものでなければならない。手に馴染むとは、手が抵抗なく受け入れているということだろう。手が欲しがるような、手が勝手に判断して知らないうちに掴んでいるようなそんなものだろう。カリフォルニア大学のドナルド・A・ノーマンという認知科学部の教授は、大学での研究に現実味がなく、実際のもの作りに対してもあまりに影響力がないと不満が募り、大学を辞めてアップルに入った。機械や装置がいかにそれらを使用する人間の認知や行動習性を無視したものかを指摘し、それがその後のアップルの商品に生かされている。 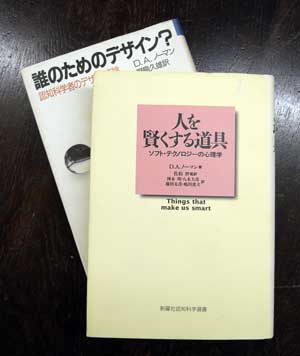 ここにドナルド・A・ノーマンの執筆した2冊の本がある。1990年に書かれた「誰のためのデザイン 認知科学者のデザイン論」と1996年執筆の「人を賢くする道具 ソフト・テクノロジーの心理学」がある。テクノロジーは人間中心でなければならないはずが、人間が機械の気まぐれに付き合っている。日本の技術は素晴らしい進化を遂げているのに、テクノロジーのデザインを技術信奉者に任せっきりにしてきた点にある。どんなに先端的技術が開発されても機械中心のものであってはならない。 ここにドナルド・A・ノーマンの執筆した2冊の本がある。1990年に書かれた「誰のためのデザイン 認知科学者のデザイン論」と1996年執筆の「人を賢くする道具 ソフト・テクノロジーの心理学」がある。テクノロジーは人間中心でなければならないはずが、人間が機械の気まぐれに付き合っている。日本の技術は素晴らしい進化を遂げているのに、テクノロジーのデザインを技術信奉者に任せっきりにしてきた点にある。どんなに先端的技術が開発されても機械中心のものであってはならない。デジタルの恩恵をこうむった道具たちは、人間と調和のとれたやり取りができるようになるべきで、テクノロジーを人間に合わせることが最も重要だと説いている。そうするには説明の文字や記号は必要ない自然なシグナルを使うデザインが、基本コンセプトでなければならない。 SRは30年目にして改悪された。クルマのミニやフィアットの変貌をなぜ参考にしなかったのか。これらはそのもののアイデンティティをしっかり受け継いで、コンセプトとエッセンスのあふれた第二世代を、時代の要請とともに作られた。数年前にコンセプトバイクとして発表された「さくら」をベースに、なぜ開発しなかったのだろうか。30年前に設計されたフレームに無理やり押し込めたテク ノロジーがむしろ可愛そうだ。早く、第二世代のSRが認知心理学をもとに開発されることを望まれる。 |